
自宅に置けなくなった家具を、あなたならどうするだろうか?
人にあげたり処分することもあるかもしれないが、大切なものは保管しておきたいと考えるはずだ。
そんな時に役に立つのがトランクルームだが、さまざまな保管方法や注意点があるので知っておこう。
ここで詳しくお伝えしていくので参考にしていただきたい。
トランクルームの基本情報

トランクルームの料金相場を知ろう
大切な家具の保管には、トランクルームの活用をおすすめしたい。
トランクルームは安全性が高く、24時間利用可能な施設も多いため、長期保管にも適しているからだ。
家具を預ける際は、サイズに合ったスペースを選び、防湿対策も忘れずにおこなうことが重要だ。また、初期費用や月額料金を比較して、自分に合ったプランを選ぶべきである。
料金相場を把握することで、予算内で最適なサービスを選択できるだろう。
初期費用には敷金や保証金が含まれる場合があり、事前に確認する必要がある。
月額料金はスペースの広さや立地条件、設備によって異なるため、複数のトランクルーム会社を比較検討することがおすすめだ。
契約手続きも簡単なので、引っ越しやリフォーム時の一時的な保管場所としても便利である。
| トランクルームの種類 | サイズ (目安) | 月額料金の相場 |
| 屋内型 | 0.5帖程度(1.6㎡) | 3,000円~8,000円 |
| 1帖程度(3.3㎡) | 8,000円~15,000円 | |
| 2帖以上(6.6㎡) | 15,000円~30,000円 | |
| 屋外型 | 1帖程度(3.3㎡) | 5,000円~10,000円 |
| 2帖程度(6.6㎡) | 10,000円~20,000円 | |
| 4帖以上(13.2㎡) | 20,000円~40,000円 | |
| 宅配型 | 小型ボックス | 1,000円~3,000円 |
| 中型ボックス | 3,000円~6,000円 |
サイズ別に見るトランクルームの容量
トランクルームのサイズごとに容量の目安を表にまとめたので、参考にしていただきたい。それぞれのサイズで収納可能な荷物の例も紹介している。
| サイズ (帖数) |
容量の目安 (立方メートル) |
収納可能な荷物の例 |
| 0.5帖 (1.6㎡) |
約2.5~3.5立方m | 段ボール箱10個程度、小型家電、衣装ケースなど |
| 1帖 (3.3㎡) |
約5~7立方m | 段ボール箱20個程度、シーズンオフの衣類、スーツケース |
| 2帖 (6.6㎡) |
約10~13立方m | ソファ、小型テーブル、複数の段ボール箱、アウトドア用品 |
| 3帖 (9.9㎡) |
約15~20立方m | シングルベッド、冷蔵庫、洗濯機、大型段ボール複数 |
| 4帖 (13.2㎡) |
約25~28立方m | ダブルベッド、ソファ、大型家電、家具一式 |
| 6帖 (19.8㎡) |
約35~40立方m | 一人暮らしの家財全般(ベッド、冷蔵庫、洗濯機など) |
サイズに応じて収納できる量が異なるので、目的や収納物に合わせて適切なサイズを選択することが重要だ。
例えば、季節物の衣類や小型家電の一時保管には0.5帖程度、引っ越しやリフォーム時に家財を保管する場合は3畳以上の広さが必要になるだろう。
家具の保管にトランクルームが最適な理由
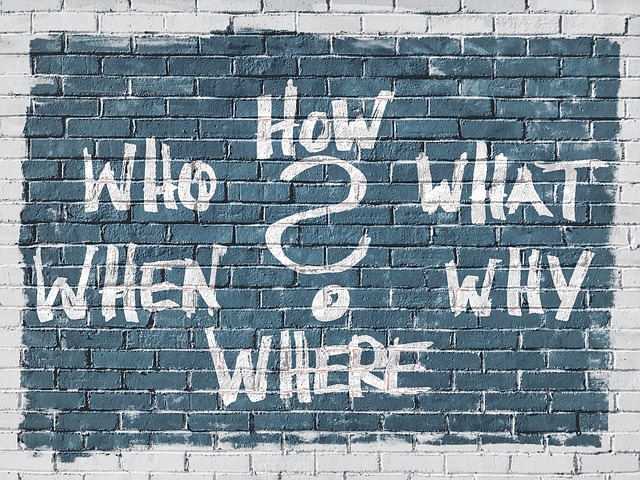
家具を保管する理由はさまざまであるが、共通して言えるのは自宅に置けなくなったという点である。
その荷物を保管するのに適した環境がトランクルームだ。
ではなぜ家具の保管に適しているのかというと、借りるのが容易で保管環境も良いからではないだろうか。
例えば引っ越しを想像してみてほしい。
受け入れ先とのタイミングが合わなくなってしまったり、引っ越し先に持ち込めないと、保管場所を探すのが大変になる。
トランクルームなら倉庫ほど大げさでもなく、利用料金もリーズナブルである。
引っ越しだけでなく海外赴任や留学、移住などで家具の保管場所を確保する必要に迫られることもあるだろう。
もし数ヶ月~年単位の長期になった場合、アパートやマンションを引き払ってしまうと荷物の置き場所が確保できない。
そうかといって部屋を借りたままにしておくのは、お金が勿体ないと考えるのが普通だ。
ベッド、ソファー、タンス、そして机やイスなどの家具は、すでに生活の一部になっている。
それだけに、きちんと保管しておく必要がある。
それには保管に適した環境であり、あなたにも簡単に利用できるのがトランクルームと言える。
3つの保管方法とそれぞれの長所・短所
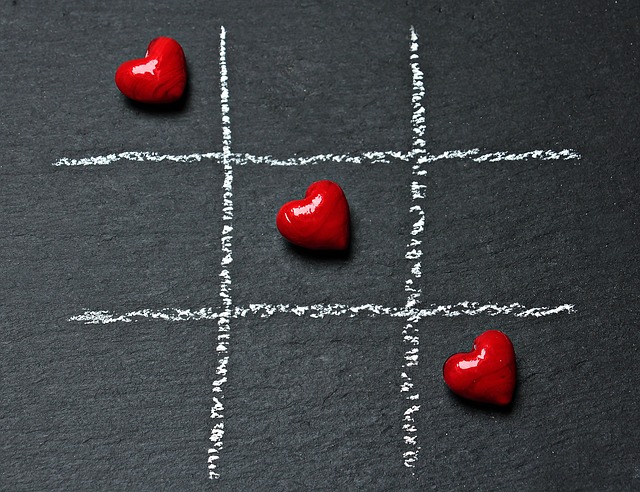
トランクルームを借りて保管
よくあるのが自分でトランクルームを借りて保管する方法だ。
ご存じのように屋内型と屋外型があるので、どちらが良いか迷ってしまうかもしれない。それぞれの特徴を判断しよう。
広さで迷った時はトランクルームのサイズを選ぶ方法!ピッタリとゆったり2つの考え方も参考にしていただきたい。
また、実際に見学して広さや出し入れに問題がないか確認しておくことも必要だ。
屋内型トランクルーム
屋内型はビルなどのフロアを間仕切りして、トランクルームとして使用するタイプになる。
環境としては自宅に置くのと大きな違いはないだろう。特に空調で温度と湿度が管理されていれば、これ以上の環境はないのでおすすめである。
比較的長期の保管でも心配はいらないと言えるだろう。
ただし屋外型と比較すると割高になるのと、十分な広さがないと大型のタンスなどを運び込むのは難しいかもしれない。
また、エレベーターや階段、通路が使えないと利用は厳しそうだ。
屋外型トランクルーム
屋外にあるコンテナタイプのものになり、出入口まで車で行けるので出し入れが楽にできる。
1階であれば大きな大型家具の出し入れも問題ないだろう。
ただ、どうしても外気の影響を受けやすいため、長期間の保管となるとカビの心配がある。そこで乾燥剤や除湿剤を上手に使って湿気から守ってあげよう。
どちらかと言えば比較的短期の保管に向いているタイプである。
料金は屋内型よりも安く、サイズも豊富にそろっているので家具がたくさんあっても収納可能だ。
専門業者のサービスを利用する
家財道具など一式を預かってくれるサービスを利用することもできる。
引っ越しの一時保管だけでなく、自宅の新築や海外赴任といった場合の長期保管までしてくれるのだ。
そして作業のすべてを業者がおこなってくれるため、おまかせするだけで実にお手軽に済んでしまう。
保管場所も専用の倉庫を使い、空調も備えていたりするので、保管環境としては十分に合格ではないだろうか。
もちろん置き方や広さを考える必要など一切ない。
至れり尽くせりなので一見いい事ずくめのようだが、短所がないわけではない。
それは費用が割高になることである。
保管料金だけでなく作業料金も加わるため、家具が多かったり、大きかったりすると、それだけ時間も手間もかかってしまう。
当然ながら料金も割高になるので、予算に余裕があればおすすめできる方法と言える。
実家や兄弟などの縁者に預ける
その他の方法として、実家や兄弟に保管をしてもらうことも考えられる。
ただし先方の都合もあるので、あくまでも可能性の話である。当たり前だが置き場所が確保できなければ保管もできない。
また、場所が離れ過ぎていても現実的ではない。
仮にあなたは東京に住んでいるとしよう。そして極端かもしれないが実家は九州で、兄弟は北海道にいるとしたらどうだろうか。
無理ではないが費用や手間を考えると、やはり難しそうである。
それに、もしも家具のカビが発生したり傷んでしまうと、お互いに気まずい思いをするかもしれない。
そうなると、実家や兄弟に保管してもらうとすれば、比較的近いところにいる場合で、短期間に限定するのが良いことになる。
家具を傷めないために注意すべきことは?

家具を傷めないように保管するするにはどんな点に注意したらよいのだろうか。
まず、大切なのは梱包をして傷めないようにすることだ。エアーキャップなどを使って、全体を包んで保護してあげよう。
この時に乾燥剤や除湿剤を入れて湿気対策と取っておくと良い。
なるべく床に直置きしないように、スノコを敷いて家具と床の間に空気が流れるようにする。
長期になるほど湿気がこもり易くなるので、通気が良くなるようにきちんと対策しておきたい。
また、害虫の発生を防ぐために防虫剤も入れておこう。
特に木製や布製になると害虫が付きやすいので、被害を受けないよう予防することが大切だ。
大切な家具を保管するのは大変なことかもしれない。しかし事前に対策をしておくことで、良い保管環境を保つことにつながるのである。
トランクルームの選び方と注意点
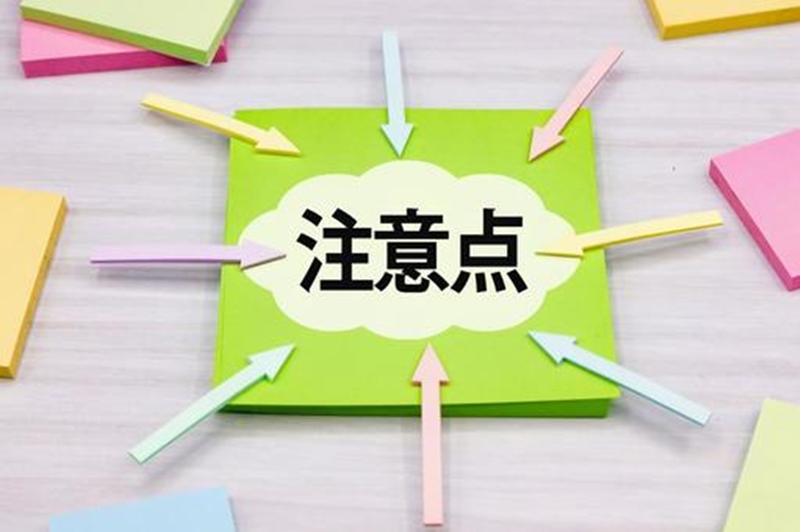
荷物に合ったサイズの選び方
トランクルームを利用する際、荷物に合ったサイズ選びは非常に重要と言える。
家具の保管を検討しているなら、まず収納する家具の寸法を正確に測定しよう。
例えば、ソファやダイニングテーブルなど大型の家具を預ける場合、2帖以上の広さが必要となることがある。
トランクルーム業者によっては、1帖~8帖以上まで多様なサイズを提供しているため、自分の荷物量に適したスペースを選ぶことが大切だ。
また、無駄な空間を借りて余計な料金を支払わないよう、収納計画をしっかり立てると良いだろう。
さらに、高さや形状にも注意し、効率的に家具を配置できるサイズを選定することで、保管コストを抑えることが可能になる。
初期費用と月額料金の比較
トランクルームを選ぶ際、初期費用と月額料金の比較は必ずおこなうようにしたい
初期費用には保証金や事務手数料が含まれる場合が多く、これらが初月の負担を増やす要因となっている。
一方、月額料金はサイズや立地によって大きく異なることがあり、都市部では高めの傾向が見られる。
例えば、一帖分のスペースでも月額7,000円、初期費用として月額料金の約2ヶ月分が必要なケースもある。
長期利用を考えるなら、更新料や解約手数料の有無も確認しておきたい。
また、初期費用0円キャンペーンや長期割引を実施していたりするので、料金体系を細かく比較し、自分のニーズに合ったプランを選ぼう。
まとめ:トランクルームを賢く利用するコツ

トランクルームを上手に利用すると、家具の保管がより効率的になる。これによってスペースの確保や費用の節約につながり、生活を快適にすることができる。
特に引っ越しやリフォームの際には大変便利と言えるだろう。
自分に合ったトランクルームを選択すれば、大切な家具を最適な環境で保管できる。そして適切なサイズや料金プランを見極めることで、無駄なスペースや費用を減らせるのだ。
また、トランクルームは安全性やアクセスの良さも重要なポイントになるのでチェックしよう。
費用についても、キャンペーンや割引を有効に活用すれば、よりお得に利用できる。
トランクルームを選ぶ際には、家具の種類や大きさ、量に応じて適切な物件を選ぶことが最も重要である。
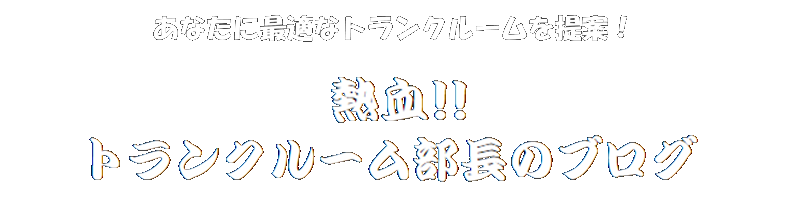


コメント